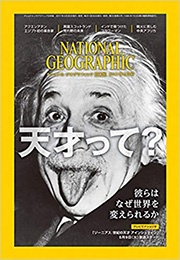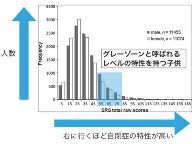スマートフォンに顔認証が採用されるように、顔はセキュリティに使えるほど「本人性」が高いものだが、情報としての顔についてはどんな研究が行なわれているのだろうか。3DCGによる顔の「再現」からエンタテインメントへの応用まで、CG研究の第一線で活躍を続ける森島繁生先生の研究室に行ってみた!
(文=川端裕人、写真=内海裕之)
ぼくたちには「顔」がある。
当たり前だ。
当たり前すぎて、深く考えることは少ない。
誰かを思い起こすとき、大抵は顔を思い浮かべる。もちろん、その人のぬくもりや、匂い、あるいは何か特徴的なパーツ、さらには「タマシイの形」などを想起する人もいるかもしれないが、それは、よほどお互いに親しい関係か、視覚以外の感覚が鋭敏な人たちの例だろう。一般に、顔は「その人」を代表するアイコンだ。
だからこそ「顔」は日常的な言葉でもおもしろい使われ方をする。「業界の顔」「顔パス」「顔が広い」というのは、象徴的な意味合いが強いし、さらに「顔を貸す・借りる・売る」などといった表現を考えてみると、「顔」に宿る「本人性」みたいなものが重要視されていると分かる。ゆえに「顔色をうかがう」「顔に出る」「顔に書いてある」というような、コミュニケーションにかかわる言い回しにも使われる。
最近では、技術的な話題として、スマートフォンなどで使う「顔認証」が普及しつつある。顔はセキュリティのために使えるほど、「本人性」が高いものなのだとぼくたちは理解している。
じゃあ、こういった様々な意味あいや機能がある「顔」について、どんな研究がなされているのだろうか。様々なアプローチがありえるが、応用物理学科、つまりバリバリの基礎科学(物理学)を応用する手法で迫るラボを訪ねた。なにしろ、顔をCGで「再現」することに、大いなる情熱を注ぎ込み、ブレイクスルーを重ねているという。基礎技術的な部分から、エンタテインメントとしての応用まで、幅広く、深い世界を垣間見させてもらえそうだ。
ところは、新宿区西早稲田にある早稲田大学西早稲田キャンパス。地下鉄副都心線の駅からキャンパス内に直結する出口があり、地上に出ると最初に眼に入るのが目指す建物だった。
研究室の主である森島繁生教授にお会いするために指定された部屋に向かったところ、最初に出会ったのは森島教授ではなく、学生さんたちだった。夕方遅かったにもかかわらず多くの学生さんたちが、それぞれの席で熱心にパソコンの画面と(おそらくは自分の研究対象と)向き合っていた。
本来の教授室は隣りにある。しかし、そっちのドアは締め切られており、学生室を通ってからでないと教授室に行けないようにしてあった。だから、最初に学生さんに会うのは正しいルートで、その後、ぼくはすんなり森島教授の部屋に迎え入れられた。

大きなモニタの前にあるミーティング用の大テーブルで相対し、森島教授はまずはこんなふうに説き起こした。
「顔の研究というのは、もう僕は30年くらいやってますけど、通信から始まっているんです。顔って、情報伝達の手段として、端的に感情を伝える手段だったり、意図を伝える手段だったり、表現として非常になじみが深いものですよね。だから、ただ音声だけで話すのでなくて、話している相手の顔が見えるようにしたいという研究でした」
これは今聞くと、何を言っているんだろうという話だが(スカイプなりほかのアプリなりで、簡単に実現できている)、30年前はまったく環境が違った。
1980年代のおしまいの頃である。

電話の回線は基本的にはアナログで、光ファイバーが個人宅にくることなどありえなかった。かろうじてISDNというデジタル通信サービスが登場していたはずだが、普及しているとは言い難く、「インターネット」という言葉を知る人も日本ではほとんどいなかった。そんな時代に、電話回線で「顔を送ろう」というのである。
「狭帯域なので普通に送ってしまうとコマ落ちしてカクカクして使えたものじゃないんです。それをいろいろ工夫していたわけですが、結局は送れなくて、そこで発想を転換して受信側と送信側にCGモデルというか、アバターを置いておいて、しゃべった言葉を代弁してくれるようにすれば、全部の画像を忠実に送らなくてもコミュニケーションは成り立つんじゃないかと考えました」
つまり、音声はそのまま送るにしても、画像については、話している人がどんな感情状態にあるのか、あるいは何をしゃべっているのかといったシンボリックな情報だけ送ってやると、受信側に置いてあるCGの本人そっくりな人物モデルが、なりかわってしゃべりかけてくれるというようなしくみだ。
「当時、これは知的通信と呼ばれて、ちょっとしたブームになりました。それまでの通信の概念は、信号を統計的な性質に基づいて符号化するというものでしたが、知的通信では、伝送される信号が持っている情報の意味内容に立ち入って伝送方式を切り替えるわけです。そのために、知識処理や人工知能技術も必要でしたし、CGについていえば、この時に本人のモデルを合成するためにやっていた研究が後に顔のCG的な研究につながっていきました。あるいは送信部分を深めていく中で、顔の認証的な研究にもつながっていったんです。でも、最初のとっかかりは、やっぱり通信だったんですよ」
アバターが代弁してくれるシステムはなかなか面白くて、いったんこういうことが実現してしまうと、じゃあアバターは本人じゃなくても、いいんじゃない? イカツイおじさんより、きれいな女性にしましょうとか、そっちの方面にも話が転がりうる。しかし、ここでは深入りせずに、森島さんのゴールの一つが「顔のCG」という方面にひとつ設定されたということを強調しておく。また1980年代の一世代前の人工知能ブームにも棹さすものだったと記憶しておこう。その上で、30年後の森島研が、現在進行形のテーマとしてかかわっていることに注目していこう。
「最近うちが掲げているゴールは、こと顔のCGでいうと、Sayaレベルのクオリティの顔のCGを自動生成することです」
「顔のモデリングをどんどんリアルにしていくと、リアルになればなるほど違和感が増して、いわゆる『不気味の谷』に落ちるよって話があったんですが、でも最近、このSayaというキャラクターが、それを超えたと話題になっています。作者は、TELYUKAさんっていう人たちで、彼らは、このクオリティのCGを、既存のレンダリングツールなり、モデリングツールなりを使いこなして、それこそ採算度外視で、とても時間をかけて作っています。あくまで手作業で、彼らなりの表現能力というか、感性で表現されたタッチですとかを、つきつめたクオリティです。じゃあ、どうやったらこのレベルのものを自動生成できるか、今一緒に研究をしようとしているんです」
Sayaは特定のモデルがいるわけではなく、あくまでデジタルで作られた3DCGなのだが、言われなければそう思えない、あるいは、言われても実写に見えてしまうほどのリアルさがある。また、特筆すべきなのは「SayaのSayaらしさ」という個性が、単に顔の造作というレベルではなく、仕草や表情のレベルでもしっかりあってドキッとさせられる。つまり、Sayaの顔は、顔が持つ「本人性」のようなものも見事に表現している。
では、森島さんのチャレンジがどこにあるかというと──
「Sayaの場合は、未知というか、実在しないキャラクターです。あくまでTELYUKAさんたちの頭の中にあるSayaっていうアイデンティティを持った、誰も知らない人物です。でも、僕たちがやろうとしているのは、実在の人物のCGなので、リアルにできたけどなにかちょっとおかしいとか、そういうことが起きるかもしれないんです。そのときに顔を忠実に再現するだけでなく、表情の本人らしさとはなんだろうとか、ということも課題になります」
なるほど、Sayaの本人らしさはクリエイターによって付与されたものだが、森島さんが目指すのは実在の人の顔CGで、表情も含めて本人らしくということなのだ。さらに自動生成、ということも目標にするから、ハードルは高そうだ。
そこに至るまで、どんなステップがあるのか、伺っていくことで実はかなり遠く、かつ、面白い地点まで到達することになりそうな予感がする。

つづく
(このコラムは、ナショナル ジオグラフィック日本版サイトに掲載した記事を再掲載したものです)
本連載からは、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた近著『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)をはじめ、「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)がスピンアウトしている。
ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。
この記事はシリーズ「研究室に行ってみた」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。