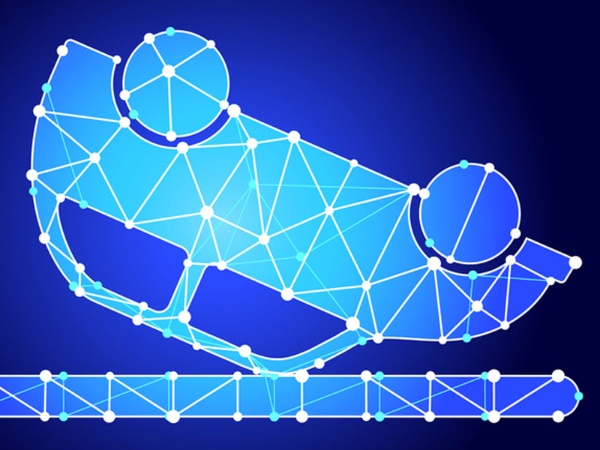小さな会社には「競争下で生き残る」のではなく、「競争のない世界で生きる」ことが求められる。不毛な価格競争を避け、「戦わない経営」を実践している企業がある。広島市の酒商山田だ。「逆転の発想で新しい市場を探し、共存共栄できる道を開く」と語る山田淳仁社長。値引きしない、営業しない、シェアを拡大しない……。すべてを「逆転の発想」で捉え、競争のない場所で存在価値を高めた。

(写真:橋本真宏、以下同)
「吹けば飛ぶような酒屋」が、売上高9億円超の企業に変わった。広島県内に4店舗を構える酒商山田(広島市)だ。
思い切った業態転換で家業を成長させたのは4代目の山田淳仁社長。「幼い頃から争いが苦手」という山田社長が目指したのは、価格競争の激しい商品を捨て、新たな需要をつくり出すことだった。
山田社長が大手損害保険会社を辞め、家業の小さな酒屋に戻ったのは1989年。ビールとタバコが9割を占めていた当時の売上高は1億5000万円。店が港に近いこともあり、ビールの大口顧客は地元の船会社だった。
家族以外に社員1人、パート1人、アルバイト2人と限られた人手のなか、船の出港時刻に合わせたビールの配達や売れ残ったビールの引き取りに追われた。ビールの値下げ要求も頻繁にある。父が購入した土地の借入金を抱え、家族経営の酒屋は経営難が続いた。
顧客を奪う営業をやめる
山田社長は大口顧客に頼らず、売り先を増やそうと考えた。しかし落胆するような出来事が続く。
知り合いの好意で受けたビールの注文には、同業者から「お客さんを取られた」というクレームの声が上がった。また、話題の純米吟醸酒を取り寄せ「珍しい酒あります」と書いた新聞の折り込み広告を配布したところ、「何をしでかすか分からない」と業界の会合で指摘された。
ある日山田社長は気づく。「今のやり方では、自分の店の売り上げを伸ばすことは、他店の顧客を奪うことと同じだ。取った取られたの争いは好きではない。戦いはやめよう」。
以来、他店の顧客からの注文は、あらかじめ他店の了解を得てもらったうえで受けることにした。また、広告宣伝や飛び込み営業など、一切の営業活動をしないことに決めた。
将来像と逆張りの経営へ
酒屋として、どう家業を続けていくべきか。酒販業界を取り巻く環境に目を向けると、山田社長が地元に戻った89年は、酒類小売免許の規制緩和が始まった年。いずれ審査に通れば誰もが酒類を販売できるようになる。酒屋の行く先が危ぶまれていた。

「酒屋の将来像は2つと言われていた」(山田社長)。1つはコンビニエンスストア、もう1つはディスカウントストアだ。
「もしコンビニエンスストアを選べば、祖父の代から築いた『のれん』がなくなる。しかしディスカウントストアとしてやっていけるほどの購買力はない。それに商品の価値を下げる安売りという形態に違和感がある」(山田社長)。
どちらも進むべき道ではない。そこで逆の発想をしてみた。きっかけは、中学校3年生のときに父が買ってきた糸川英夫氏の『逆転の発想』という本。「たまたま風呂場の前にずっと置いてあった。逆転の発想という言葉だけが頭にずっと残っていた」(山田社長)。
すると、答えが見えてきた。
商品を次々に追加し、利便性を追求するコンビニの逆となるのは、商品の種類を絞った店だ。また、売れる商品を大量に仕入れ、安価で販売するディスカウントストアの逆は、知られていない小さな造り手の酒を定価で販売することだ。そこに自店の活路を見いだせるように感じた。
縮小市場の商品を充実
山田社長は、コンビニやディスカウントストアなどで買える商品を捨てることにした。商品全体の95%を占めていたビール、タバコ、日本酒(普通酒)の販売だ。まずビールの値引きをやめて、その売り上げを徐々に減らし、代わりに日本の酒──吟醸酒などの日本酒や焼酎に注力した。なぜ日本の酒にしたのか。
広島県内には、日本の酒に特化した店はなかった。また、日本酒のマーケットは縮小傾向にあった。小さい市場なら手ごわい競争相手も来ない。戦わずに存在価値を見いだせるはずだと考えた。日本酒と本格焼酎の魅力を伝えていくこともできる。
しかしここからが長い道のりだった。山田社長が売ろうと決めたのは有名な蔵元の酒ではない。無名でもおいしい酒を造っている酒蔵を見つけ、一緒に銘柄を育てていく。そのため、仕入れ方法から売り方まですべてを変えた。
これまで問屋から調達していた酒は蔵元から直接仕入れることにした。「造り手の考えを知ることができるし、お客様の要望を伝えることもできる」。
小さな蔵元に電話をかけ続け、電話の向こうで、酒造りの夢を語り合える相手とは取引を決めた。「安酒のイメージを払拭したい」という蔵元の要望を聞けば、年月をかけて新たな酒造りを応援し、全国の店に紹介することもあった。
しかしすべてがうまくいったわけではない。「せっかく取引が始まっても私たちの力不足でお客様がつかないこともあったし、取引が一度きりで終わってしまうこともあった」(山田社長)。たとえそうであっても、一度結んだ縁を自分からは切ることはなかった。ようやく日本酒が動き始めたという手応えを感じたのは、7年後だ。
90年には芋焼酎の扱いを開始した。「森伊蔵」だった。当時広島では芋焼酎を飲む文化がなかった。そのため、せっかく醸造元を説得して商品を仕入れたものの鳴かず飛ばずの時期が続く。倉庫にはついに30箱が山積みになったこともあった。売れ行きを心配した社長から電話があるたび、「おかげさまで売れています! いつもありがとうございます」と嘘の返事をし続けた。
焼酎が順調に売れるようになったのはそれから5年がたった頃。やがて2002年の本格焼酎ブームで一気に火が付いた。
アドバイスを売る
山田社長は言う。「私たちの役割は、造り手の思いや情熱を伝えるだけではなく、蔵元の付けた価格に見合う、あるいはそれ以上の価値と特徴を見いだし、日本の酒の素晴らしさを世の中に広めていくこと」。

そのため2つのことを徹底している。1つは一物一価を崩さないこと。90年代に始まった規制緩和によって、山田社長の予想通り、価格競争と価格破壊が激化した。しかし、もし価格を下げれば、造り手の思いや情熱までディスカウントすることになる。価値を守るため、90年以降、酒商山田では一切安売りをしていない。個人向けにも飲食店にも、醸造元が決めた定価で販売をしている。
2つ目は、顧客や得意先に対し、酒ではなくアドバイスを売ること。店に来る顧客の要望を細かく聞き、イメージに合う1本を選び抜く。それだけではでない。造り手の様子や人柄が伝わる話を伝えるなど、顧客の知的好奇心を満たす付加価値を添える。
また贈答用の酒には、贈り手の思いを描いたオリジナルのラベルを提案し、1枚1枚手作りしたこともある。常にプラスアルファを意識したサービスを届けている。
飲食店に対しては、店が繁盛するアドバイスを心掛ける。そのため、客単価、お酒の予算や原価率、店のコンセプト、メニューを聞いて酒を選んでいる。
ウィン-ウィンで発展
「日本酒が売れるようになる一方でビールの販売量が減る。その差で売り上げを1億円増やすのに13年かかった。日本の酒の売り上げが9割を超したのは2000年」(山田社長)。
2004年には法人化した。現在県内に異なるコンセプトの4店舗を構え、全国の醸造元362社、飲食店1600店と取引をしている。ほとんどが口コミで広がった客だ。2016年3月期の売上高は9億4570万円。
山田社長が大切にしてきたのは「お客様、お得意様、蔵元と私たちがともに成長・発展するウィン-ウィンの関係」。蔵元と一緒においしい酒ができればいい蔵が増え、お客様が喜び、市場が大きくなり、自分たちも成長できる。
山田社長のもとには今、経営の仕組みを学びたいと相談者が国内外から続々と訪れている。農業関係者、海外の流通企業など、業種はさまざまだが、ともに繁栄したいという思いは同じ。コラボ商品を発売するなど、酒商山田の周りで新しい取り組みも生まれている。戦いを必要としないビジネスモデルが今、実を結んでいる。
(この記事は、「日経トップリーダー」2017年11月号に掲載した記事を再編集したものです)
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。
この記事はシリーズ「ベンチャー最前線」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。





![[対談]「悪さができない少年」が「好き」を仕事に変えるまで](https://cdn-business.nikkei.com/atcl/seminar/19nv/00124/00062/s800.jpg?__scale=w:192,h:144&_sh=0e00bc0103)