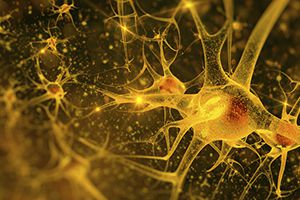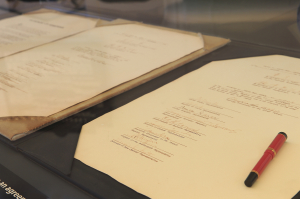あの戦争とは何だったのか。
あれが「防衛のための戦争」であったという見方は根強くある。しかし他方で、あれが「侵略戦争だった」と言われれば、そう思われる歴史的な筋もないことはない。
そのように世の中を二分するような全く異なる見解があるとき、正邪を軽々しく論ずるわけにはいかない。いずれの立場にも考えがあり、部分的に見ればそれぞれの主張には論拠があるからだ。あの戦争の背景にはかなり複雑な要因があった。それは、70年の時を経た今なおそう思う。
一口に言えば、日本人はそもそも浮き上がっていた。それは誰も否定できないはずだ。
私もその中の一人である。1941年の末に太平洋戦争が始まり、まだ20歳にも満たなかった感受性の強い時分の私は、いわゆる「興亜青年」のはしくれだった。「日本は神国である」という極めて単純な考え方──あまりに神がかり的で、独善的な思想がその背景にあった。
そもそも日本の近代とは、欧米の帝国主義的脅威に対する恐怖と反発の歴史だったともいえる。私が生まれて間もない頃、日本は第一次世界大戦後の深刻な恐慌に見舞われ、たくさんの農村の娘たちが遊郭に売られていった。それほど窮乏していたのだ。若者たちが、欧米列強によるアジア侵略の歴史にいちじるしく正義感を刺激されるには十分な、時代の空気があった。
本当に日本が神国でほかの国が野蛮であったのか、それは違うんじゃないか──そうしたことには思いいたらなかった。
私は苦学して大学に進み、欧米諸国の植民地政策の歴史とそれを変革する方法について学びたいと望んでいた。しかし、戦争勃発によりそれは叶わなかった。間もなくして私は占領地における指導者を養成するための訓練所に入所し、アジア諸国や諸民族の歴史や現状を学ぶことから、言語の習得、剣道や武道の鍛錬ならびに国粋主義の精神教育を受け、優秀な成績で訓練を修了した。
1942年の暮れに海軍ニューギニア民政府に採用されたときには、まさかそこが修羅の戦場になるとは夢にも思っていなかった。一介の愛国青年として、尊王の大義に従い、アジア民族解放のために戦うという理想に燃えていた。18歳で戦地に赴くとき、尊敬する吉田松陰の墓を参り、「松陰先生、どうか私にも貴方がたどられたと同じ危難を与えてください」と祈りを捧げた。純情といえば純情、馬鹿といえば馬鹿だ。そこには紙一重の差しかない。
太平洋戦争中の二百数十万人にも達する戦死者数のうち、最も多いのは敵と撃ち違えて死んだ兵士ではない。日本から遠く離れた戦地で置き去りにされ、餓死した兵士たちなのだ。100万人を超える飢えて死んだ兵士の、その無念がどれほどのものか、想像できるだろうか。
第二次世界大戦中、生存率7%といわれ、最も過酷を極めたニューギニア戦線を、私はかろうじて生き残った。ニューギニア島は日本から南に約5000キロ、オーストラリアのすぐ北にある大きな島だ。面積は日本のおよそ2倍、全体が熱帯雨林に覆われ、現在は島の東側がパプアニューギニア、西側がインドネシアの一部になっている。昼間でも太陽の光が届かない原生林に飢えと疲労が蔓延し、マラリアやアメーバ赤痢などの伝染病を併発した兵士たちが次々と野垂れ死んだ。意外に思われるかもしれないが、熱帯雨林にはバナナなどの果実がたわわに実っているわけではない。映画や漫画の世界とは違って、現実でまともに食べられるものといえば、先住民が栽培している農作物だけだった。補給は長く保たず、兵士は草の芽やは虫類を口にした。
極限状態で、人間とは思えない残酷で愚かな行為がなされた。捕虜の虐待も凄惨であった。それは日本兵だけはない。相手側にも人道に悖る行為が山のようにあった。そうした状況は、太平洋戦域のいたるところで、戦いが始まってすぐの頃から戦後にいたるまで、繰り返し発生した。
終戦を迎え、私は進駐してきたオランダ軍に逮捕され、BC級戦犯としてゲリラ処刑の罪に問われた。猛獣をつなぐような鉄の鎖をかけられて、現地の裁判所に移送され死刑を求刑されたが、最終的に「重労働20年の刑」を受けた。勾引される直前にただ一度、拳銃で自決を考えたが、仲間にさとられて未遂に終わった。それ以後、私は自分の運命に逆らわないことにした。
三畳一間、四方を分厚いコンクリートの壁に囲まれて、銃殺刑の恐怖と戦いながら、私は命がけで本を読み勉強した。狭い独房に光が射す。本のページを繰るごとに、人間としての感性が甦ってくるようだった。
あの戦争は日本の一方的な侵略戦争だったのか、あるいは防衛戦争だったのか。具体的な事実に即して一つ一つ論証する必要があると思った。魂を切り刻むような苦しみに耐えて、考えに考えて、反省に反省を重ねて、煉獄の苦しみを味わった。
何よりも残酷だったのは、やってしまった行為ではなくて、そうせざるを得なかったという一連の成り行きを理解することだった。大東亜戦争の意義を信じて戦場でやってきたことを、全て否定せざるを得なかった。自分の全存在を否定しないと立ち直れないという葛藤。それがどれほど辛いことか、あなたにおわかりだろうか。
だが、今振り返ってみれば、これ以上の勉強の場はなかった。
身を投げて自殺を試みた人間も、何人かいた。みんながみんな、自分の行動について振り返り苦しんでいたかどうかはわからない。敵の復讐のために戦後の報復裁判で俺は殺される──そう考えることは死者に対して大変失礼だ。ある意味でいちばん安直なその考え方に囚われて、そのまま死んだ者も大勢いる。
当時、自分と同じような状況で、若い学徒兵だった大槻隆君がこんな歌を詠んだ。
つきつめて 己に帰る 悲しみを
放つに狭き 壁あつき部屋
戦争のことを忘れるどころではない。日々、身を切り刻むような思いで過ごしてきた。それが、私にとっての戦後70年だ。
朝から晩まで身を切り刻む思いをして人間は生きられるわけはない。しかしそれに耐え、私は後の世を生きる若者たちにあの戦争の記録をきちんと残しておきたい。その思いは日々募るばかりだ。もちろんこれは極めて荷の重い仕事である。しかし、野垂れ死にした兵士たちもまた、それぞれ未来に夢を抱いていた若者だった。彼らの無念の思いを代弁しなければならない。それを伝え得る、私は最後の一人だからだ。
今、私は92歳、もう余命いくばくもないどころではない。
最近、うれしいことがあった。
4年前、私は島根県の山奥にある高校に頼まれて、特別授業を行った。明治時代の無教会派のキリスト教徒、内村鑑三の教えを受けて創立された、山奥の小さな、小さな学校だ。出雲空港から車で2時間以上かけてようやくたどり着いたその学校に3日間滞在し、生徒たちと胸を突き合わせて戦争体験を語った。私たちはいくらでも語り合った。語り合わずにはおれなかった。生徒からぴんぴんと、生きた反応が返ってくるんだ。あんなに手応えのある語り合いは初めてだった。そしてたくさんの生徒が感想文を書いて送ってくれた。私は涙がこみ上げるのを押さえることができなかった。長い間、壁あつき部屋にいた私の人生の、それは一縷の救いであった。
その生徒たちの中にいた一人の青年が、今SEALDsという団体のリーダーとして、何万人もの人々を率いて平和を求めるデモをしている。この間、彼がうちに来て「あのとき、僕は飯田先生の目の前に座って話を聞きました」と言うんだ。彼が高校生のときに記した感想文には「次に先生に会ったとき、先生から投げられたボールを返せるように生きていきたい」と書かれていた。私が投げたのは、ほんの小さなボールでしかない。だが、見ず知らずの学生に投げたそのボールが今、予想もしない大きなうねりとなっている。
こんなに素晴らしいことがあるか。
一体何が人間にとって最も望ましい生き方なのか、92歳になった今もよくわからない。人にはさまざまな生き方がある。さまざまな生き方が望ましいんだ。70億の人間の中には平気で人を殺す連中もいれば、そうでない者もいる。だがしかし、みんな必死になって生きている。それぞれ信じる道を歩んでいる。必死になって、己を正しいと信じた道を歩むのは、正しい。
だから、私はかつて自分が信じた「正しさ」の暗部と向き合い、あなた方に伝えたいと思う。
嫌なことには目を向けたくない習性が、人にはある。しかし、この習性は個人には許されても、国家や民族には許されない。70年前のことをすっかり忘れる集団健忘症は、また別の形で、より大きな過ちを繰り返させるものだと、私は危惧する。
日本がこれからどうなっていくのか、それは私にはわからない。現に日本国の総理大臣は、私の思いとは全く違う道を歩み、国民を引っ張ろうとしている。しかし、国民はそれを許さないだろう。
世界を見渡せば失望、あるいは絶望する要素はいくらでも見つけることができる。しかし、逆もまた真なり。 人間の未来を考えたとき、私は若い人たちに希望を託さざるを得ない。
だから、あなたたち一人一人に伝えたい。 心の中に壁厚き部屋を持ち、ものごとを深く考え、真理を追究しなさい。 そのうえで、それぞれが大いに遊べ。大いに人生をエンジョイしろ。
またとない人生の、生きる喜びを享受しなさい。これが、あの戦争を生き残った私からの最後の言葉だ。